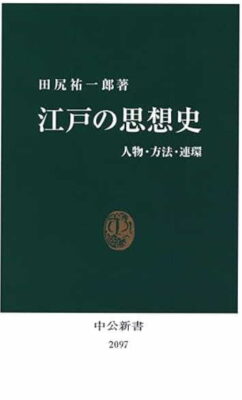こんにちは、なおじです。
今日も本との出会いにワクワクしております。
日課の本屋巡りをしていて見つけた本書『江戸の思想史 人物・方法・連環』、いやぁ〜これは参りました。
家に帰ってXを眺めていると、フォロワーが**「水戸学にも触れてるよ〜」**なんて投稿しているではありませんか 。
水戸に住む身として、少なからず水戸学に興味を持っている私には見逃せない一冊。
著者の田尻祐一郎さんを調べてみると、なんと水戸生まれ!
同郷の研究者が江戸思想史を語るとなれば、これは即座にKindle版をポチッと。


本書の全体像 – 13章で辿る江戸思想の系譜
本書は序章から第13章まで、実に充実した構成になっています:
| 章 | タイトル | 主なテーマ |
|---|---|---|
| 序章 | 江戸思想の底流 | 内藤湖南・網野善彦の史観と「世俗的秩序化」 |
| 第1章 | 宗教と国家 | 宗教一揆への対応と「神国」イデオロギー |
| 第2章 | 太平の世の武士 | 『葉隠』と忠の思想 |
| 第3章 | 禅と儒教 | 「無心」と「自由」、熊沢蕃山の経世論 |
| 第4章 | 仁斎と徂徠(1) | 朱子学批判と古典学の方法論 |
| 第5章 | 仁斎と徂徠(2) | 他者の発見と社会構想 |
| 第6章 | 啓蒙と実学 | 貝原益軒、宮崎安貞、新井白石 |
| 第7章 | 町人の思想・農民の思想 | 安藤昌益、二宮尊徳の社会批判 |
| 第8章 | 宣長-理知を超えるもの | 国学の大成と「もののあわれ」論 |
| 第9章 | 蘭学の衝撃 | 『解体新書』翻訳と都市知識人 |
| 第10章 | 国益の追求 | 経世家たちの富国強兵論 |
| 第11章 | 篤胤の神学 | 平田篤胤の神道体系 |
| 第12章 | 公論の形成-内憂と外患 | 幕末期の思想的展開 |
| 第13章 | 民衆宗教の世界 | 天理教など新宗教の台頭 |
これだけの章立てで江戸思想史を俯瞰するなんて、
十三章 栞が足りず 指を挟む
といった具合ですね(笑)。
序章「江戸思想の底流」- 世俗的秩序化という核心
内藤湖南と網野善彦の史観継承
序章では、著者の基本的な視座が示されます。
内藤湖南の「応仁の乱を境とする中世・近世区分論」と、網野善彦の「職人・商人・芸能民に注目する社会史」を継承しながら、江戸時代を「世俗的秩序化」の時代として捉える独創的な視点を提示しています 。
中世までの「恐怖の闇に囲まれた苛酷な暮らし」から、「屋根の下で家族に看取られて死を迎える」ことが普通になった近世への転換。
これを単なる制度変化ではなく、人々の心性レベルまで掘り下げて分析する手法は圧巻です 。
中世は 風邪で遺書書く 当たり前
考えてみれば、江戸時代の人々の方が、現代の私たちより「死」や「家族」について真剣に考えていたかもしれませんね。
「世俗生活への転換」という画期
著者によれば、応仁の乱以降、日本社会は根本的な変質を遂げました。
「イエ」の確立、出版文化の興隆、商品経済の発展、そして何より「日本」意識の形成。
これらは単なる制度史的変化ではなく、人々の精神世界の変容を伴う大きな転換だったのです。
第1章「宗教と国家」- キリスト教の衝撃と神国イデオロギー
ハビアンの『妙貞問答』が示すもの
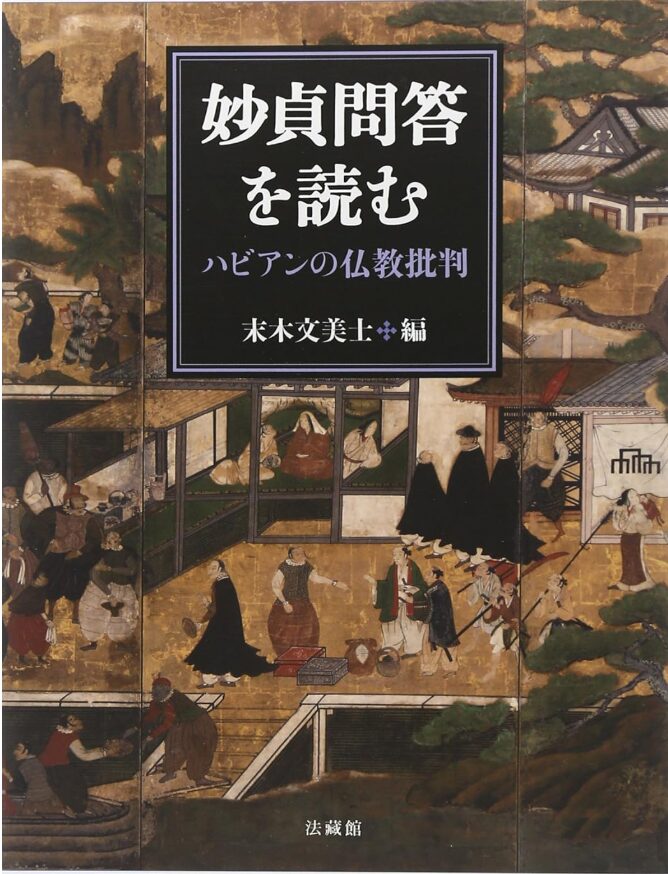
第1章では、キリスト教受容とその反動について論じられています 。
特に注目すべきは、ハビアンの『妙貞問答』の分析です。
従来の日本人が慣れ親しんだ「神」概念と、一神教の絶対神との根本的相違。
「天地万物の創造主」という発想は、「自然」的世界観に慣れ親しんだ日本人には革命的な衝撃でした。
便所まで デウス一人の 手仕事か (なおじ)
当時の日本人の発想としては、海にも山にも神がいる。
長靴にも、ひいてはトイレにだって神がいる。
八百万の神々、という認識が普通。
結局、「デウス」は日本語に翻訳できず、そのまま音写されることになったんですね。
「神国」イデオロギーの成立
キリスト教への対応過程で形成されたのが「神国」イデオロギーです。
日本を「神々の国」として位置づけ、外来宗教に対抗する論理を構築していく過程は、後の攘夷思想にもつながる重要な思想的展開でした。
不受不施派の日奥(にちおう)などの宗教的抵抗も、単なる宗派対立を超えた政治的・思想的意味を持っていたことが明らかにされています。
第2章「太平の世の武士」- 『葉隠』に見る武士道の変質
山本常朝の武士道論
第2章では、太平の世における武士のアイデンティティ問題が扱われています。
『葉隠』で知られる山本常朝の「武士道といふは死ぬ事と見つけたり」という有名な言葉の真意は何だったのか。
実戦経験のない武士たちが、いかにして武士としての存在意義を見出そうとしたかの思想的格闘が描かれています。
「忠」の概念の深化
太平の世だからこそ、「忠」という概念が抽象化され、精神化されていきました。
実際の戦場での忠義ではなく、日常の中での主君への心構えとしての忠義。
これは現代のサラリーマンの「会社への忠誠心」にも通じる普遍的テーマですね。
死ぬ覚悟 朝の茶入れに 込めてみる (なおじ)
第3章「禅と儒教」- 「無心」と「自由」の探求
熊沢蕃山の経世論
第3章では、禅思想と儒教の交錯が論じられます。
単なる政治論にとどまらず、「無心」という禅的境地と実務的な政治運営をどう両立させるかという深い問題に取り組んでいました。

「自由」概念の萌芽
江戸前期にすでに「自由」という概念の萌芽が見られることは驚きです。
もちろん現代的な個人の自由とは異なりますが、既成の権威や慣習にとらわれない思考の自由への志向は確かに存在していました。
これは後の蘭学や国学の発展にもつながる重要な思想的土壌だったのでしょう。
第4章「仁斎と徂徠(1)」- 朱子学批判と古典学の方法論
伊藤仁斎の革命的方法論
第4章からは、江戸思想史の白眉ともいえる仁斎と徂徠の分析に入ります。
伊藤仁斎の古典解釈学は本当に画期的でした 。
「血脈」(思想の内容的骨格)と「意味」(書物の特定箇所での意味内容)を区別し、まず直感的に「血脈」を把握してから個々の「意味」を精密に検討していく循環的読解法。
これ、現代の私たちが古典を読む際にも極めて有効な方法論なんです。
朱子学の相対化
仁斎の最大の功績は、朱子学を絶対視せず、孔子・孟子の「古義」に立ち返ろうとしたことです。
これは単なる復古主義ではなく、既成の権威を批判的に検討する近代的な学問精神の現れでした。
古典を読むのは「困典」を読むようなものですが、仁斎の方法論があれば、難解な古典も身近な友人のように感じられるはず。
【第1部はここまで。続きは中編でお届けします】