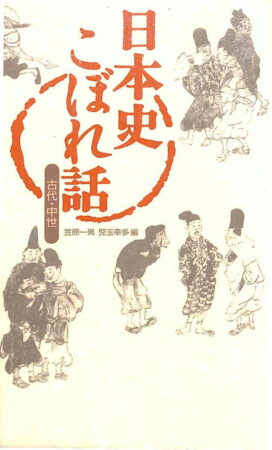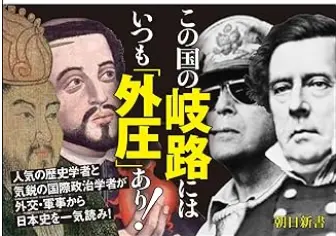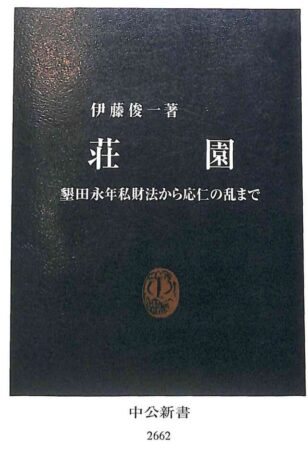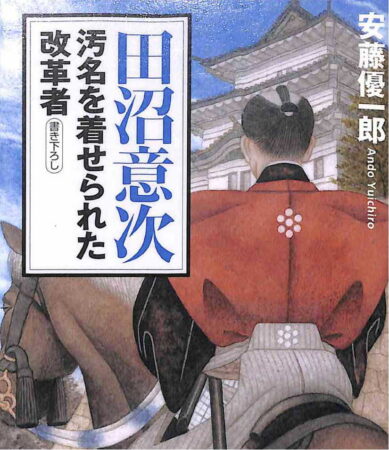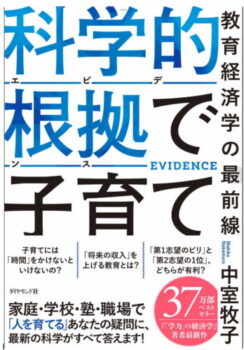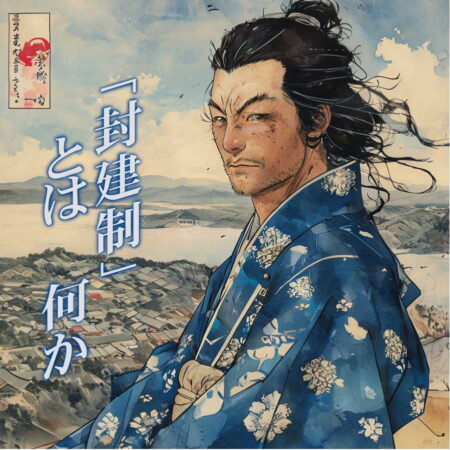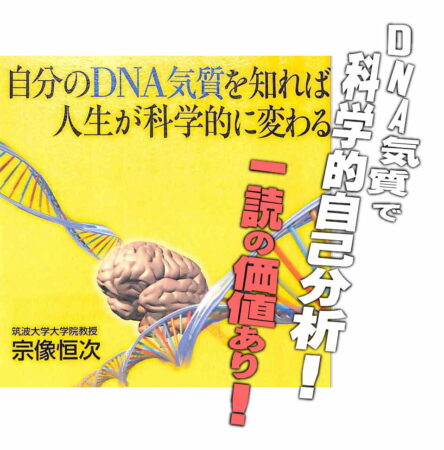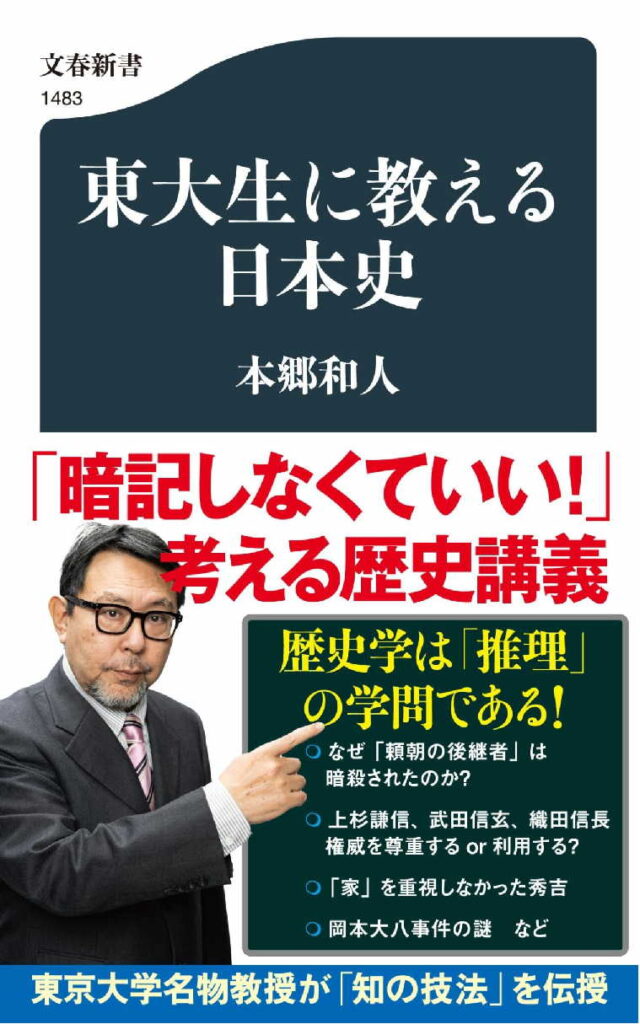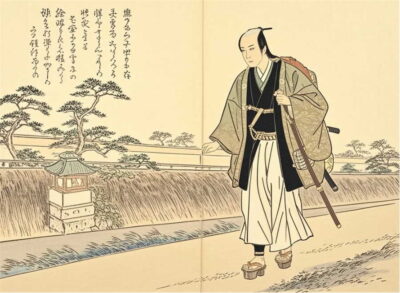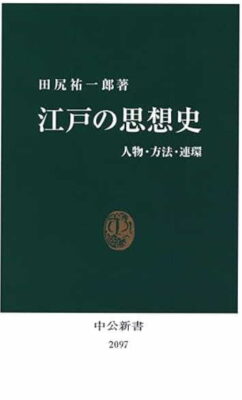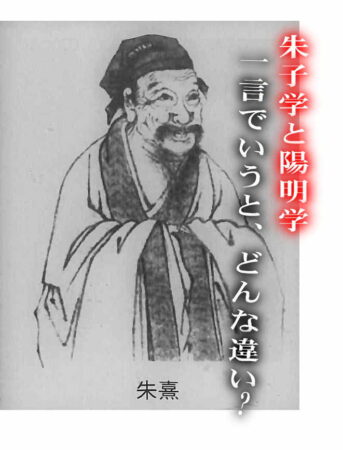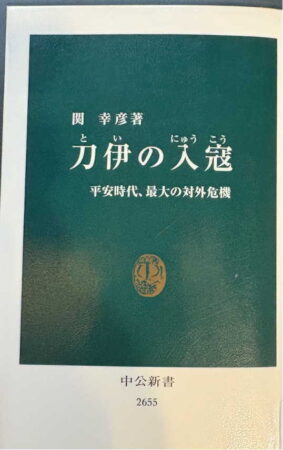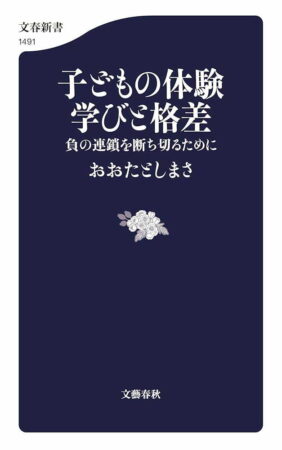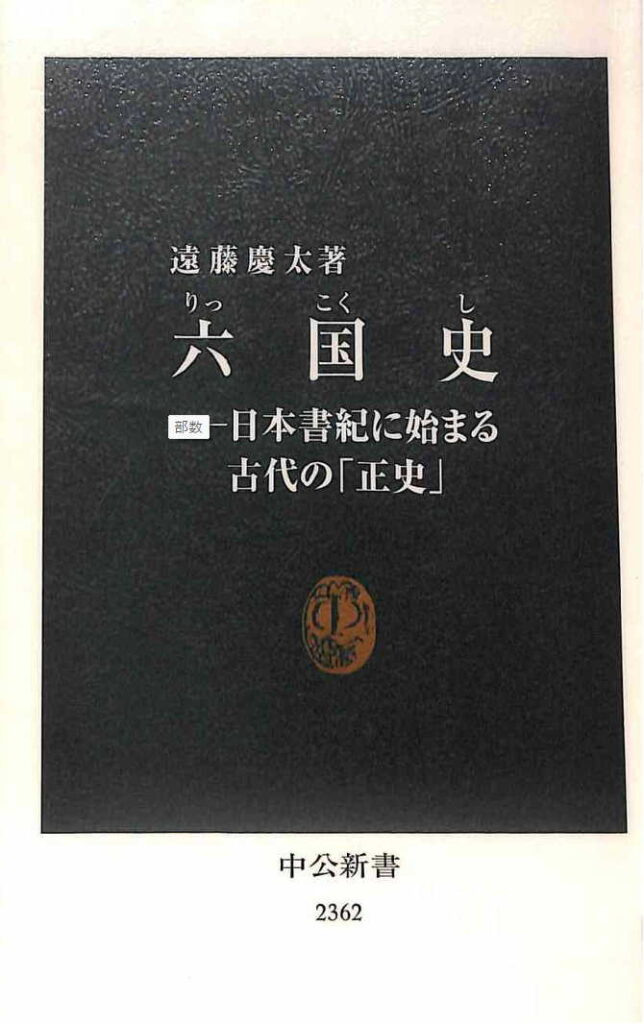元教師が驚いた『外圧の日本史』書評(後半)|鎖国から敗戦まで対談で読み解く
こんにちは、なおじです。 本郷和人さんと簑原俊洋さんの対談『「外圧」の日本史』を読んで驚きました。 家康が日本を弱くしたって、まさかそんな見方があるなんて! この記事は前記事『外圧の日本史』の続編で、江戸時代の鎖国から太平洋戦争の敗戦までを...
『「外圧」の日本史』書評:本郷和人と簑原俊洋が解き明かす日本の国家形成【前編】
こんにちは、なおじです。 外圧が日本の歴史を動かしてきたという視点から日本史を読み解く試みが注目を集めています。 本郷和人氏と簑原俊洋氏による『「外圧」の日本史 白村江の戦い・蒙古襲来・黒船から現代まで』(朝日新書、2023年)は、古代から現代...
田尻祐一郎『江戸の思想史』書評📚【中編】思想家たちの「人生相談」が面白すぎる件
こんにちは、なおじです。 前編では序章から第4章まで読み進めましたが、いやあ、中編に入ると俄然面白くなってきました。 なぜって、江戸の思想家たちが取り組んでいたのは、結局のところ現代の私たちと同じ「人間関係の悩み」だったんですから。 社会科...
田尻祐一郎『江戸の思想史』書評📚【前編】水戸出身研究者が描く江戸思想家の格闘
こんにちは、なおじです。 今日も本との出会いにワクワクしております。 日課の本屋巡りをしていて見つけた本書『江戸の思想史 人物・方法・連環』、いやぁ〜これは参りました。 家に帰ってXを眺めていると、フォロワーが**「水戸学にも触れてるよ〜」**な...
『朱子学と陽明学』書評 – 3度目の正直で見えてきた東洋思想の真髄【徹底再読記】
基本情報 📚 タイトル:『朱子学と陽明学』著者:小島毅出版社:筑摩書房(筑摩eブックス)出版年:2015年ジャンル:東洋思想史・哲学 なぜ今、この本を読み返したのか 🤔 実は恥ずかしい話なんです。 この本、過去に2度も読んでいるんですよ。 キンドルで購...
【書評】平安時代最大の危機を元教師がゆる〜く解説!『刀伊の入寇』📚
📖 基本情報 項目内容タイトル刀伊の入寇 平安時代、最大の対外危機著者関幸彦出版社中央公論新社出版年2021年8月ジャンル日本古代世史・軍事史 こんにちは!元社会科教師の、なおじです 😊 2024年に放送された大河ドラマ「光る君へ」、ご覧になりましたか?...
🎯 大名行列の起源は村上義清の「車懸り」?まさか戦国必殺技が優雅な行列の正体だった!
元社会科教師で旅好きのなおじです。 次の旅先を考えていた時、ふと村上義清の名前が頭に浮かんだんですよね。 「そうだ、義清が最後を過ごした根知城に行ってみよう」と旅の計画を立てながら、昔読んだ本のことを思い出しました。 「確か村上義清の車がか...
📚 元社会科教師なおじが震えた!本郷和人『東大生に教える日本史』で歴史が100倍面白くなった話
どうも、元社会科教師のなおじです。 「先生、日本史って暗記ばっかりでつまんないです」 教員時代、生徒たちからこんな声を何度聞いたことか。 そのたびに「いやいや、歴史は面白いんだよ」と説得しようとしても、どこか説得力に欠けていた自分がいました...
『子どもの体験 学びと格差』を読んで感じたこと〜社会科教師35年の本音
書籍情報 項目内容タイトル子どもの体験 学びと格差 〜負の連鎖を断ち切るために〜著者おおたとしまさ出版社文芸春秋(文春新書)出版年2024年ジャンル教育・社会問題 この本との出会い〜青い表紙が語りかけてきた〜 こんにちは、こんばんは! 社会科教師...
【書評】古代日本の「真実」!『六国史』で1300年前の宮廷ドラマ覗き見
こんにちは、なおじです! 歴史って「難しそう...」って思ってませんか? でも実は、古代の宮廷って現代のテレビドラマ顔負けの人間ドラマが満載だったんです。 今日は、そんな古代日本の「リアル」が詰まった一冊をご紹介します! 📚 基本情報 項目内容タ...
さぁ、始めよう。