こんにちは、なおじです。
前編では序章から第4章まで読み進めましたが、いやあ、中編に入ると俄然面白くなってきました。
なぜって、江戸の思想家たちが取り組んでいたのは、結局のところ現代の私たちと同じ「人間関係の悩み」だったんですから。
社会科教師時代、生徒から「なんで勉強するんですか?」とよく聞かれました。
江戸の思想家たちも同じような疑問と格闘していたんですね。



第5章「仁斎と徂徠(2)」- 日本初の社会学者誕生?

荻生徂徠という「空気の読めない天才」
松岡正剛の「千夜千冊」によると、荻生徂徠(1666-1728)は現代でいう「空気を読まない論理派」でした。
当時の常識をバッサバッサと切り捨てる様子は、職員会議で提案を片っ端から却下する同僚を思い出します(笑)。
徂徠が発見したのは、今でいう「社会システム論」です。
個人がいくら頑張っても、システムが悪ければうまくいかない。
現代のブラック企業問題と本質的に同じことを、300年前に指摘していたんです。
「古文辞学」という画期的読書法
徂徠の読書法は現代でも使えます:
- 原典主義: 解説書ではなく、直接原典を読む
- 歴史的視点: 書かれた時代背景を重視
- 文脈重視: 前後の流れを大切にする
私も生徒に「まず教科書より史料を読め」と言っていましたが、徂徠先生の方が300年先輩でした。
古典読み スマホ予測が 古語ばかり
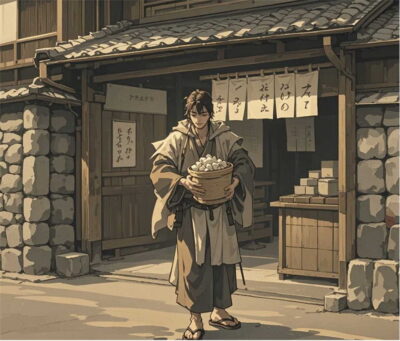
第6章「啓蒙と実学」- 江戸版「ライフハック」の誕生

貝原益軒の「健康オタク」ぶり
貝原益軒(1630-1714)は、現代でいう「健康情報にうるさいおじいちゃん」でした。
『養生訓』を読むと、まるで現代の健康番組を見ているようです。
中国の医学書をそのまま信じず、日本の気候や体質に合わせて内容を修正。
これって現代の「ローカライゼーション」そのものですよね。
妻に「また健康の話?」と言われる現代のお父さんたちの先駆けかもしれません。
あそれ、わたしのことかも…。
新井白石の「合理主義おじさん」
新井白石(1657-1725)は、神話を「そんなバカな!」と科学的に検証した人です。
古事記の神話を読んで「これは何かの暗喩でしょ?」と冷静に分析。
現代でいうと、都市伝説を検証するテレビ番組のMCみたいな人だったのかも。
第7章「町人の思想・農民の思想」- 江戸時代にもいた「意識高い系」

安藤昌益という「究極のエコ活動家」
安藤昌益(1703-1762)の思想を読むと、現代の環境活動家も真っ青です。
昌益の理想社会「自然世」:
- みんなで農作業(万人直耕)
- 身分差別なし(四民平等)
- 自然との調和重視
これって、現代の「持続可能な社会」「SDGs」の先駆けじゃないですか。
300年も前にこんなこと考えてたなんて、恐れ入ります。
二宮尊徳の「現実主義コンサルタント」
対照的に二宮尊徳(1787-1856)は、理想より現実を重視。
報徳思想は現代の「経営コンサルタント」そのもの:
- 勤労: まずは働こう
- 分度: 身の丈に合った生活を
- 推譲: 余裕があれば人のために
昌益が「理想論を語る大学教授」なら、尊徳は「現場で汗をかく経営者」でしょうか。
改革論 家計簿前で 小さくなり
第8章「宣長-理知を超えるもの」- 日本語オタクの大発見

本居宣長という「国語の鬼」
本居宣長(1730-1801)は、現代でいう「言語学オタク」でした。
古事記を35年かけて注釈するなんて、普通の人にはできません。
宣長が発見した「やまとことば」の美しさは、現代の私たちにも響きます。
漢語ばかりの堅い文章より、和語中心の柔らかい表現の方が心に残るのは、宣長のおかげかもしれません。
「もののあはれ」の深さ
宣長の「もののあはれ」論は、現代の「感情知能」に通じます。
理屈では割り切れない人間の複雑な心情を大切にする視点は、AI時代の今こそ必要ですね。
私も授業で生徒の「なんとなくモヤモヤする」という感情を大切にしていましたが、宣長先生が理論的裏付けをくれていたんですね。
改めて、この本で発見!
読書は、自分で気づかずにやっていたことを改めて発見させてくれる時がある。
これ、本当に至高の瞬間。
第9章「蘭学の衝撃」- 江戸版「カルチャーショック」

『解体新書』が与えた衝撃
杉田玄白らの『解体新書』(1774年)は、まさに「パラダイムシフト」でした。
それまでの常識が一気にひっくり返る体験は、現代でいうとインターネット普及レベルの衝撃だったでしょう。
中国医学で「気」だ「経絡」だと言っていたのに、西洋医学では内臓が精密に描かれている。
これはびっくりしますよね。
都市知識人の誕生
蘭学の普及で生まれた新しいタイプの知識人は、現代の「グローバル人材」そのもの:
- 専門知識に長ける
- 世界情勢に敏感
- 実証的思考を重視
江戸時代にもいたんですね、こういう人たち。
翻訳本 読んで畳が 狭く見え
第10章「国益の追求」- 江戸版「成長戦略」
本多利明の海洋国家論
本多利明(1743-1820)の『経世秘策』は、現代の「経済成長戦略」を先取りしていました:
- 海外貿易の推進
- 産業の育成
- 人口増加政策
現代の政府の経済政策と変わりませんね。
時代を超えて、政策課題は共通するんでしょう。
まとめ – 江戸の思想家たちの「人生相談」
田尻祐一郎さんの『江戸の思想史』を読んでいると、江戸の思想家たちが取り組んでいたのは、結局「どう生きるか」「どう社会とつき合うか」という永遠のテーマだったことがわかります。
✨ 現代に通じる格闘:
- 徂徠の社会システム論 → 組織論・経営学
- 宣長の感情重視 → 感情知能・心理学
- 蘭学の実証主義 → 科学的思考法
- 経世論の現実主義 → 政策立案・経営戦略
社会科教師として約40年間、生徒たちの相談に乗ってきましたが、彼らの悩みと江戸の思想家たちの問題意識は驚くほど似ていました。
後編では、平田篤胤の神学と幕末の激動期に入ります。
江戸思想史のクライマックスをお楽しみに!


参考文献
- 田尻祐一郎『江戸の思想史:人物・方法・連環』中公新書、2011年
- 松岡正剛「1653夜『江戸の思想史』」千夜千冊
シリーズ記事
- 前編:序章から第4章「江戸思想の基盤」
- 中編:第5章から第10章「思想家たちの格闘」(この記事)
- 後編:第11章から第13章「近代への扉」(次回更新予定)