4. 革新的な3つのキーコンセプト〜歴史の見方が180度変わる
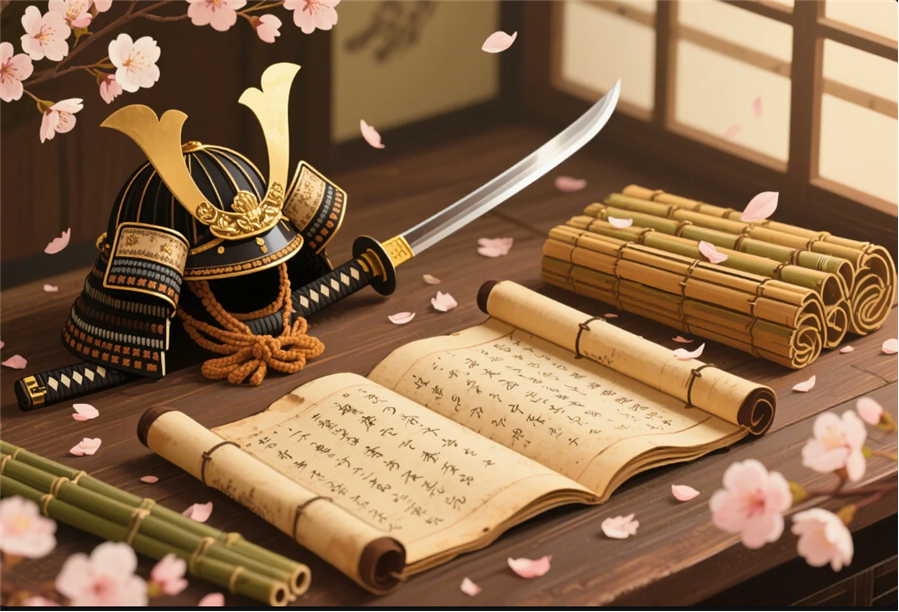
結論:複雑な歴史用語も、本郷先生にかかれば「なるほど!」に変わります。
4-1. 「一職支配」という概念
これまでの日本史では、土地の権利関係が複雑で分かりにくかったですよね。
家系図を見ているような混乱状態 😵
でも本郷先生の「一職支配」という概念で、すっきり理解できます:
| 従来の土地支配 | 一職支配 |
|---|---|
| 本家、領家、地頭等が複雑に絡み合う | 領主が土地・人を一元的に支配 |
| 誰が本当の「所有者」か曖昧 | 明確な所有権の確立 |
| 二重課税の危険性 | 信長・秀吉が推進した革新システム |
4-2. 「在地の台頭」という視点
従来の歴史は「中央vs地方」という構図で語られがち。
でも本郷先生は**「横の結合」**に注目します。
例えば一向一揆:
- 単なる農民の反乱ではない
- 同じ階層同士が水平的にネットワークを形成
- 惣村→惣郷→惣国という広域連合
この視点で見ると、歴史の見え方が全然違ってきます。
地図を上から見ていたのが、突然横から見るようになったような感覚です。
4-3. 「兵農分離⇔兵農融合」のダイナミズム
武士と農民の関係も、単純な「分離」だけでは説明できません:
- 戦国時代:農民兵の大量動員で軍事力飛躍的向上
- 秀吉の兵農分離:武士の城下町集住、刀狩りで農民武装解除
- 明治の徴兵制:再び兵農融合へ、「国民皆兵」実現
この循環的な視点が新鮮でした。
歴史って実は螺旋階段のように、同じようで少しずつ違う段階を踏んでいるんですね。
でも、これらの概念だけでは物足りない方もいるでしょう。
本郷先生の真骨頂は「通説バスター」にあります 💪
5. 本郷流「通説バスター」の痛快さ〜常識をひっくり返す爽快感
結論:信長再評価論は、まさに法廷ドラマのような緊張感で展開されます。
5-1. 信長は「普通の戦国大名」だった?
最近の歴史学界では「信長は革新的ではなく、普通の戦国大名だった」という説が流行。
でも本郷先生は真っ向から反論します。
従来説の問題点:
- 楽市楽座や鉄砲活用は他にも先行例があった
- 権威を否定したわけではない(天皇に献金など)
本郷説の根拠:
- 唯一「天下統一」をビジョンとした戦国大名
- 武田信玄は甲府から動かなかった
- 上杉謙信は春日山城に住み続けた
- 信長だけが本拠地を次々移転
- 兵種別編制への転換
- 従来の「家臣団別編制」から脱却
- 鉄砲隊という専門部隊の編成
この論証の仕方が実に説得力抜群!
本当に法廷ドラマを見ているような緊張感があるんです。
5-2. 秀吉の「意外な」革新性
秀吉についても目から鱗の分析。
一般的には「人たらし」「成り上がり」のイメージですが、本郷先生が注目するのは**「デスクワーク重視」**という点。
わくわくですよね、この視点!
具体例:賤ヶ岳の七本槍のその後
- 加藤清正:槍働きで有名 → 実は兵站担当で評価、肥後20万石の大名に
- 脇坂安治:槍働き一筋 → 事務仕事拒否で3万石止まり
つまり、秀吉は戦場での活躍よりも事務能力を重視していたんです。
現代のIT企業みたいですね 💻
そんな本郷先生の解説を読んでいて、思わず「あるある!」と膝を打った体験談があります。
6. 読んでいて「これは分かる!」だった個人的体験
結論:教師時代の「なぜ年号?」という疑問が、ようやく解決しました。
6-1. 教師時代の「暗記から思考へ」の衝撃
教員時代、生徒たちに:
- 1192年(いい国作ろう)鎌倉幕府成立
- 1333年鎌倉幕府滅亡
- 1336年室町幕府成立
こんな年号をひたすら覚えさせて、「意味あるの?」という顔(心の叫び!)
さらには、生徒たちからの冷たい視線… 😅
でも本郷先生は「鎌倉幕府成立は1180年(頼朝鎌倉入り)」と主張。
理由は「この時点で独自の土地安堵を開始したから」。
つまり、「いつ」よりも「なぜ」が大切ってことなんですね。
これを当時の生徒たちに教えてあげたかった…。
6-2. 「地域史を見直す」新しい視点
「在地力」という概念で地域史を見直すと、新しい発見がありそうです。
私の出身地も、確かに中世には在地の豪族がいたし、江戸時代には藩の一部として発展しました。
この視点は、現代の地方創生にも通じるものがありますね。
中央依存ではなく、地域の「横の繋がり」で活性化していく…そんなヒントが歴史の中に隠されていたとは。
でも、読書体験をさらに充実させたいなら、オーディオブック版もおすすめです 🎧
(ちなみに私は、オーディブルを使用してます。)
7. オーディオブック版の魅力〜「ながら学習」で効率アップ
結論:プロのナレーションで、本当に授業を受けているような臨場感が味わえます。
ちなみに、この本はオーディオブック版も出ています。
プロのナレーターさんが講義調のトーンで読み上げてくれるので、本当に授業を受けているような臨場感があるんです。
こんな時にピッタリ:
- 満員電車での通勤時間 🚃
- ジョギング中のお供に 🏃♂️
- 家事をしながらの「ながら学習」 🧹
私は紙の本と併用して2回読み(1回聞き)しました。
普段、こんなに繰り返して読まないんですが、1回目は「へぇ〜」、2回目は「なるほど!」という感じで。
ところでこの本、他の歴史本と比較してみると、どんな位置づけになるでしょうか?
8. 他の歴史本との比較〜圧倒的な「思考重視」
結論:「歴史の見方を根本から変えたい」なら、断然本郷本です。
8-1. VS『日本史の内幕』(半藤一利)
| 項目 | 『日本史の内幕』 | 『東大生に教える日本史』 |
|---|---|---|
| アプローチ | エピソード中心の読み物 | 体系的な歴史観の提示 |
| 読後感 | 「へぇ〜」という感想 | 「なるほど!」という納得 |
| 学術性 | 面白いけど断片的 | 論理的な思考プロセス |
どちらも面白いんですが、歴史の見方を根本から変えたいなら、断然本郷本です。
8-2. VS『47都道府県の歴史』(山本博文)
情報量:山本本 > 本郷本
議論の深さ:本郷本 > 山本本
読み物としての面白さ:本郷本 >>> 山本本
本郷本は「量より質」で勝負している感じですね。
濃厚なスープと薄いスープくらい違います 🍜
さて、この本を読むべき人、読まなくてもいい人を整理してみましょう。