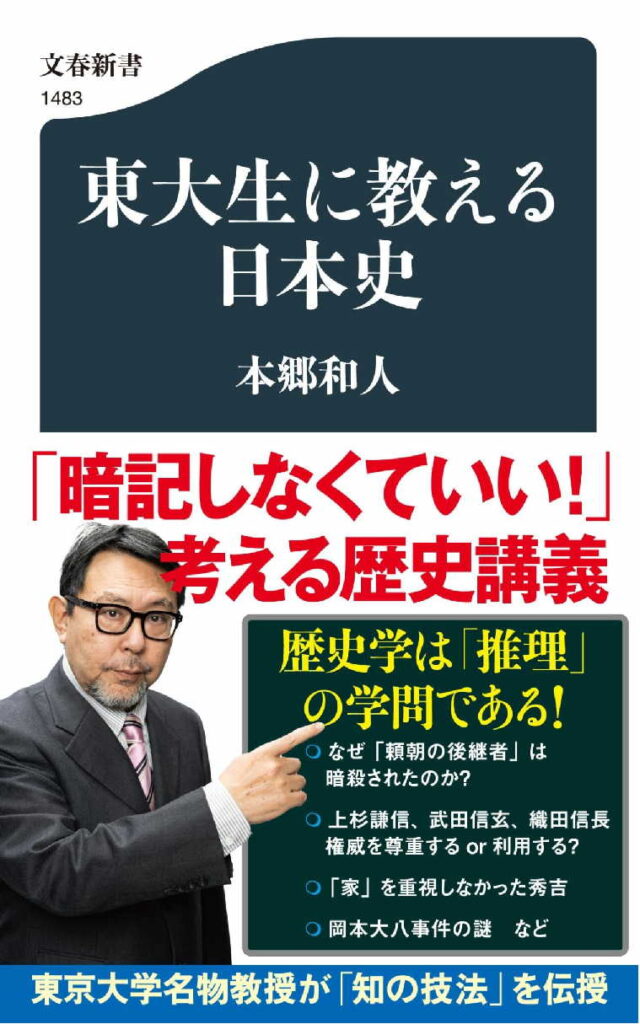
どうも、元社会科教師のなおじです。
「先生、日本史って暗記ばっかりでつまんないです」
教員時代、生徒たちからこんな声を何度聞いたことか。
そのたびに「いやいや、歴史は面白いんだよ」と説得しようとしても、どこか説得力に欠けていた自分がいました。
正直に告白すると、私自身も歴史を「暗記科目」として教えてしまっていた部分があったんです 😅
でも本郷和人さんの『東大生に教える日本史』(文春新書、2025年)を読んで、まさに目からウロコがボロボロ落ちました。
本郷先生の本は以前から気になって、書店で見つけるたびに購入していたんですが、今回も期待を裏切らない内容。
むしろ期待値を軽々と超えてきました。
「東大教養課程の講義録」という響きだけで、もう知的好奇心がうずうずしませんか?
この記事を読むとあなたのこんな悩みが解決します:
・📚 歴史は暗記科目で面白くないという固定観念から解放される
・🔍 年号や人名を覚えるだけではない「推理する歴史学」の面白さを発見できる
・💡 複雑な日本史の流れが「なるほど!」と腑に落ちるようになる
・🎯 信長・秀吉・家康の「本当の革新性」が見えてくる
・🌟 受験で挫折した日本史への苦手意識を完全に払拭できる
・📖 東大レベルの講義を手軽に体験する方法がわかる
・🧠 現代社会の問題を歴史的視点で考える思考法が身につく
・⭐ 数ある歴史本の中から本当に読む価値のある一冊を見つけられる
1. 本郷和人って何者?〜「歴史のプロ中のプロ」が教える授業の迫力
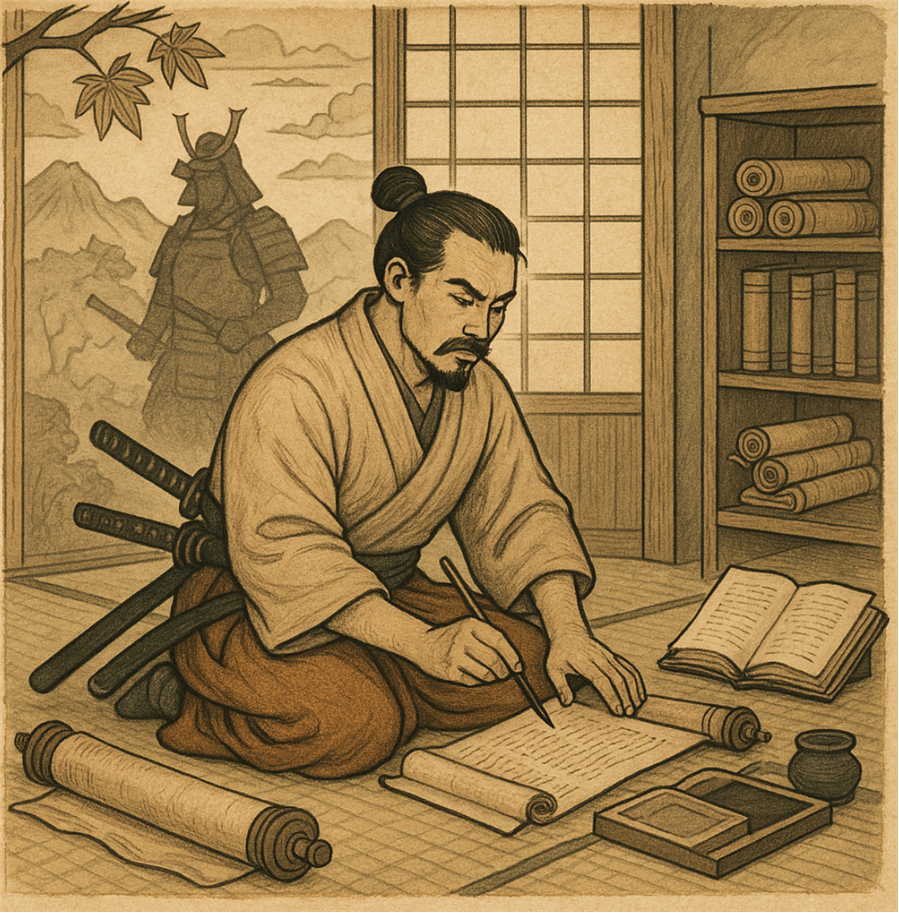
結論:本郷先生は、学術界にとどまらない「歴史を面白く伝える天才」です。
まず著者紹介から。
本郷和人さん(1960年生まれ)は東京大学史料編纂所の教授で、鎌倉中期史のエキスパート。
この方のすごいところは、学術界にとどまらない幅広い活動です。
本郷和人氏の実際の主要著書
| 書名 | 出版社・形態 | 発行年 |
|---|---|---|
| 東大生に教える日本史 | 文春新書 | 2025 |
| 東大教授が教える〈やさしい〉日本史 | 朝日新書 | 2023 |
| 歴史のプロが語る鎌倉幕府の真実 | PHP新書 | 2021 |
要するに「歴史を面白く伝える天才」なんです。
今回の新書は、2022年に東大駒場で実際に行われた連続講義をベースに再構成したもの。
つまり、東大生が受けた「生の授業」を本で体験できるということです。
これ、相当贅沢じゃないですか?
東大の講義を1000円ちょっとで受講できるなんて…高級フレンチをコンビニ弁当の値段で食べられるような感覚です。
でも、ここで疑問が湧きませんか?
なぜ本郷先生の講義はこんなに引き込まれるのでしょうか?
2. 全8回の講義構成〜なぜこんなにワクワクするのか?
結論:各回が独立しているようで、実は一本の太い線で繋がっているから。推理小説の伏線みたいです。
本書は全8回の講義+あとがきで構成されています:
📖 講義の全体像
- 第1回:鎌倉幕府の誕生 – 「武士の世の始まり」を再定義
- 第2回:頼朝の死から元寇まで – 在地の台頭と承久の乱の意味
- 第3回:室町幕府、西か東か – 京都選択の経済的理由
- 第4回:日本人と宗教 – 一向宗の「日本型一神教」論
- 第5回:信長の革新性 – 「普通の戦国大名説」への反論
- 第6回:秀吉の天下統一 – デスクワーク重視の革新性
- 第7回:家康が求めたもの – 「家の永続」という価値観
- 最終回:江戸から近代へ – 武士身分解体の必然性
各回が独立しているようで、実は一本の太い線で繋がっているんです。
🎯 本書の3つの主要テーマ
本郷先生が一貫して訴えているのは以下の3点:
- ① 歴史を動かす「潜在的な動因」を探る思考法
- 表面的な出来事の背後にある「なぜ?」を考える
- 例:コロナ禍での在宅勤務普及 → 実は以前から「毎日出勤の無駄」への疑問が潜在していた
- ② 鎌倉幕府から幕末までの「転換点」を大胆に再解釈
- 従来の通説に疑問を投げかける姿勢
- 史料を基にした論理的な推論
- ③ 暗記不要の日本史入門
- 「歴史嫌い」にこそ読んでほしい内容
- 推理小説のような面白さ
でも、本当にこれだけで歴史観が変わるものでしょうか?
答えは次の章にあります。
3. ここがスゴイ!本書の3つの革新的ポイント
結論:「推理」として歴史を捉える発想転換が、まさに革命的なんです。
3-1. 講義調の親しみやすい語り口
最大の魅力は、なんといってもその語り口の絶妙さ。
実際に教室で先生の話を聞いているような臨場感があります。
例えば、鎌倉幕府成立年問題について:
「この説の難点はただひとつ、私以外に誰も支持者がいないことです」
思わずクスッと笑ってしまうような軽妙な表現。
でも内容は超本格的。この絶妙なバランスが最後まで私を(読者を)飽きさせません。
3-2. 「推理」としての歴史学
特に印象的だったのが、本書冒頭の言葉:
「歴史は暗記の山を登る行為ではない。山の向こうで何が起きるかを推理する学問だ」
これ、まさに革命的な発想転換です。
歴史って、実は推理小説を読むような面白さがあったんですね。
3-3. 具体例による「目から鱗」体験
例えば、源義経追討の場面。
教科書では「兄弟の確執」程度にしか書かれていませんが、本郷先生は違います。
頼朝の視点から見ると:
- 東国武士が求めていたのは「土地の安堵」
- 義経は後白河上皇に取り込まれ、頼朝の戦略を無視
- これは東国政権の基盤を揺るがす大問題
つまり、個人的な感情論ではなく、政治的必然性があったというわけ。
この視点転換の鮮やかさときたら!
しかし、本当にこれだけで歴史観が変わるものでしょうか?
実は、本郷先生の真骨頂は別のところにあります。
