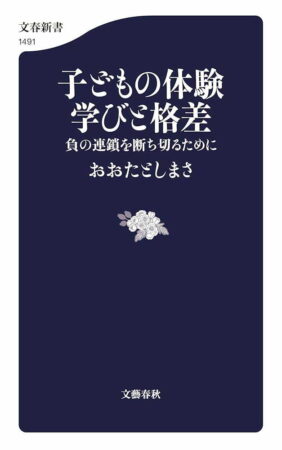
書籍情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 子どもの体験 学びと格差 〜負の連鎖を断ち切るために〜 |
| 著者 | おおたとしまさ |
| 出版社 | 文芸春秋(文春新書) |
| 出版年 | 2024年 |
| ジャンル | 教育・社会問題 |
この本との出会い〜青い表紙が語りかけてきた〜
こんにちは、こんばんは!
社会科教師として35年間、子どもたちと一緒に過ごしてきた「なおじ」です。
最近読んだ本の話をしようと思います。
教育の話になると、どうしても熱くなっちゃうんですよね😅
先日、白井俊さんの『世界の教育はどこへ向かうのか』を読んで、「うおー、これは面白い!」と興奮してしまいました。
で、その勢いで「もっと教育について学びたい!」と思って書店をうろうろしていたら、深い青色の表紙が目に飛び込んできたんです。
夜空みたいな色で、なんだかワクワクしちゃって。
「これは何か特別な本かも」って直感で手に取ったのが、この『子どもの体験 学びと格差』でした。
最初は「また格差の話か…」って思ったんですが、読み進めていくうちに「え?これって今までの常識をひっくり返すような内容じゃない?」って驚きの連続でした。
さて、ここで皆さんに質問です。「体験格差」って言葉、聞いたことありますか?
この本は、その「体験格差」について、今までとは全く違う角度から切り込んでいるんです。次の章で、その衝撃的な内容を紹介しますね。お楽しみに!😊
著者の おおたとしまささんってどんな人?
まずは著者の紹介から。
おおたさんは1973年生まれで、麻布中高から東京外国語大学に入学するも中退、その後上智大学で英語を学んだという、ちょっと波瀾万丈な経歴の持ち主です。
リクルートで働いた後、教育ジャーナリストに転身。
なんと80冊以上の本を書いているんですよ!
すごくないですか?私なんて、この年になっても読書感想文を書くのに四苦八苦してるのに😂
でも何より印象的だったのは、教員免許を持っていて、小学校での勤務経験もあるということ。
「あ、この人は現場を知ってる人なんだ」って思いました。評論家の机上の空論じゃなくて、現場の匂いがプンプンするんです。
でも、ここからが本当に面白いところです。
普通の教育本だと思って読み始めたら、最初からガツンと予想外の展開が待っていました。
次の章で、その衝撃を味わってください!
本書が投げかける衝撃的な問い
「体験格差」って本当に問題なの?
みなさん、普通に考えれば「体験格差は問題だ!なんとかしなきゃ!」ってなりますよね。
私もそう思ってました。
でも、おおたさんは違うんです。
いきなりこんなことを言い出します:
「体験格差を問題視することが、競争社会を当然のものとして受け入れることになっていませんか?」
この言葉を読んだ瞬間、頭をハンマーで殴られたような衝撃を受けました。
私たち教育者が「良かれ」と思ってやってきたことが、実は子どもたちを競争の渦にどんどん巻き込んでいたかもしれないって。
考えてみれば、「体験格差を埋めよう」という発想って、結局は「勝ち組になるための条件を整えてあげよう」ってことですよね。
これって、競争社会の土俵に子どもたちを上げることを前提にしている。
数字で見る格差の現実
でも、実際に数字を見てみると、確かに格差は存在します:
| 家庭年収 | 習い事なし | 友達と遊べない |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 69.2% | 52.3% |
| 600万円以上 | 32.1% | 18.7% |
(放課後NPOアフタースクール2025年調査より)
この数字を見ると、「やっぱり格差はあるじゃないか」って思いますよね。
でも、おおたさんの指摘は「だからといって『体験をもっと与えよう』っていうのが本当に正しいアプローチなのか?」ということなんです。
この疑問に答えるために、おおたさんは全国の現場を歩き回りました。
そこで聞いた支援団体の声が、これまた予想外だったんです。
次の章で、その驚きの内容を紹介しますよ!😉
現場を歩いて見えてきた真実

支援団体からの意外な声
おおたさんは、全国の支援現場を歩き回りました。
100年以上続く伝統的なキャンプ場から、プレーパーク、無料塾、街角の駄菓子屋まで。
そこで聞こえてきたのは、本当に予想外の声でした:
支援現場の生の声:
- 「体験格差って言葉に違和感がある」
- 「子どもたちが本当に求めているのは、もっとシンプルなこと」
- 「整えすぎた体験は、かえって子どもの自由を奪っている」
この声を聞いて、私も教員時代のことを思い出しました。
保護者から「○○力を身につけさせたい」「△△の能力を伸ばしてほしい」って相談が増えた時期がありました。
でも、そんな時の子どもたちの目って、本当に輝いていたでしょうか?
子どもたちの本当の願い
現場で子どもたちが本当に言いたいことは、こんなにシンプルなんです:
- 「もっと遊びたい」
- 「友達と自由に過ごしたい」
- 「大人に決められるんじゃなくて、自分で決めたい」
これって、すごく当たり前のことですよね。
でも、私たち大人は「それじゃあ将来困るから」って、いろんな体験を用意してあげようとする。
でも、ちょっと待って。
その「用意された体験」って、本当に子どもたちが求めているものなんでしょうか?
さて、ここで教育界で最近よく聞く「非認知能力」の話が出てきます。
おおたさんは、この概念についても鋭い指摘をしているんです。
次の章で、その目からウロコの内容を紹介しますね!✨
「非認知能力」ブームへの鋭い指摘

曖昧な概念への疑問
最近、教育界では「非認知能力」という言葉がやたらと飛び交っています。
でも、おおたさんはここでもズバッと核心を突いてきます。
「非認知能力」の問題点:
| 問題点 | 具体的な課題 |
|---|---|
| 定義の曖昧さ | 「人付き合いができる」程度のふわっとした理解 |
| 測定の困難さ | 本当に測れるのか、正直かなり怪しい |
| 介入の限界 | 外から無理やり身につけさせられるものなのか |
私も現場で研修を受けた時、「非認知能力を伸ばしましょう!」って言われたことがありました。
でも、正直「具体的にどうやって?」って思ってました。
そのモヤモヤした気持ちが、この本を読んでスッキリしました。
社会性や情動コントロールの能力って、実は膨大な認知過程があるのに、それを「非認知」って呼ぶのは変じゃないですか?
おおたさんは、この概念の曖昧さが、結局は「なんとなく良さそう」という印象だけで広まってしまう危険性を指摘しています。
この本を読んで、私がずっと感じていた現場での違和感の正体が、ついに見えてきたんです。
次の章で、その体験を共有させてください!
私がこの本を読んで思ったこと〜社会科教師35年の現場経験と重ねて〜
心に刺さった一節
本書で一番グッときた言葉がこれです:
「子どもが本来もつ『いいこと思いついた!』のような場と、評価目線を持たない複数の大人との直接の関わり合い、これらの肝要さ」
これを読んだ瞬間、「そうそう、これなんだよ!」って叫びたくなりました。
私が社会科教師として一番幸せだった瞬間って、子どもたちがキラキラした目で「先生、聞いて!」って駆け寄ってきた時なんです。
それは習い事で身につけた技能じゃなくて、自分で見つけた小さな発見の喜びでした。
現場で感じていた違和感の正体
この本を読んで、私がずっと感じていた違和感の正体がやっと分かりました。
「体験の詰め込み教育」の構造:
| 従来の考え方 | 本当に大切なこと |
|---|---|
| たくさんの体験を与える | 子どもの自発的な発見を待つ |
| 成果を測定する | プロセスを大事にする |
| 大人が先回りして準備 | 子どもの「やりたい」を尊重する |
この違いって、料理で例えると分かりやすいかも。
大人が全部作っちゃった料理と、子どもが自分で味見しながら作った料理って、味も楽しさも全然違うじゃないですか。
教室での小さなエピソード〜真の「体験」とは何か〜
私の教室で実際にあった話なんですが、ある日、算数の時間にカレンダーを見ていた男の子が突然手を上げて「先生、2月だけなんで日数が少ないんですか?」って質問したんです。
その瞬間、クラス全体が「あ、そういえば!」って盛り上がって。
結局、その日の算数は予定を変更して、みんなでカレンダーの秘密を調べる時間になりました。
これって、まさに「いいこと思いついた!」の瞬間だったんですよね。
どんな高級な体験プログラムより、子どもたちの目が輝いていました。
ここで、社会科教師として35年間考え続けてきた「体験」について、私なりの理解をお話しします。
社会科教師「なおじ」が考える「体験」の本質
実は、この本を読んで改めて気づいたことがあります。
「体験格差」って議論する時、みんな「活動」の部分ばかり注目しがちなんですが、それって半分しか見てないんじゃないかって。
私は長年、**「体験 = 活動 + そこから生まれる気づき」**だと考えてきました。
例えば、社会科の授業で地域の商店街を見学に行ったとします。
でも、ただ歩いただけじゃ「活動」でしかない。
大切なのは、その時に子どもたちが何に気づくかなんです。
子どもたちの気づきは宝物だけど、すぐ消えちゃう
面白いことに、子どもたちって必ず何かしらの気づきをするんです。
「あ、この店、お客さんが少ないな」「看板が古くなってる」「でも、おばあちゃんが笑顔で話してる」とか。
しかし、その気づきって本当に淡いもので、子ども自身も自分がなんて言ってたのかすぐに忘れちゃうんですよ。
だから私たち教師は、子どもたちの小さなつぶやきや表情を見逃さないように、アンテナを高くしておかないといけない。
そして、その気づきを「みんなで考える問題」にしてあげるのが、教師の一番大切な仕事だと思うんです。
「体験」と「経験」の違い
ちなみに、私は「体験」と「経験」を分けて考えています:
- 体験:個人的で主体的な気づきのレベル
- 経験:クラスで話し合って、みんなで深めた客観的な知識のレベル
一人の子の「2月って短いな」という体験(カレンダーを眺めるという活動を通して得た気づき)が、クラス全体で「なぜ2月は短いのか」を調べる経験に発展する。
これが本当の学びなんじゃないかな。
この私の体験のとらえを踏まえると…正直、この本にも物足りなさを感じる部分があります。
著者の問題提起は素晴らしいんですが、現場の人間としては「じゃあ明日から何をすればいいの?」って思っちゃう部分も。
次の章で、その辺りの建設的な批判をしてみますね。
